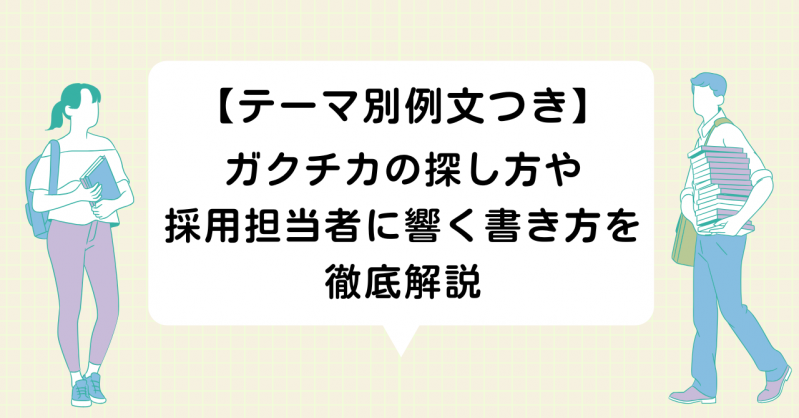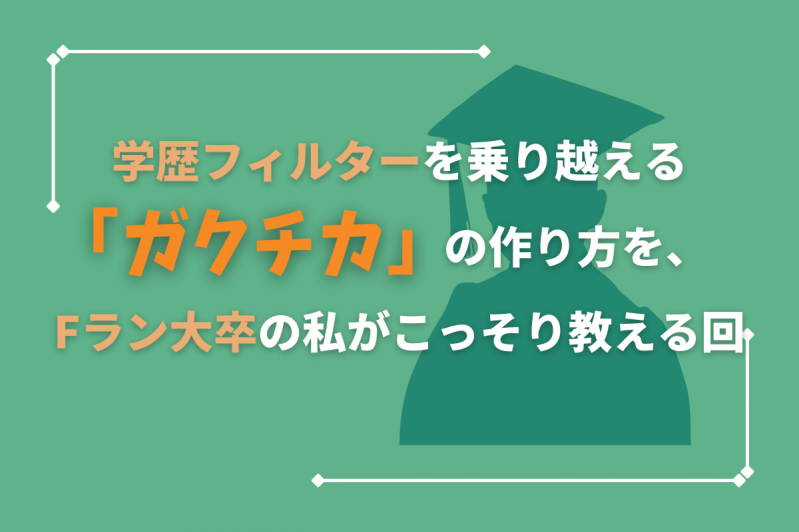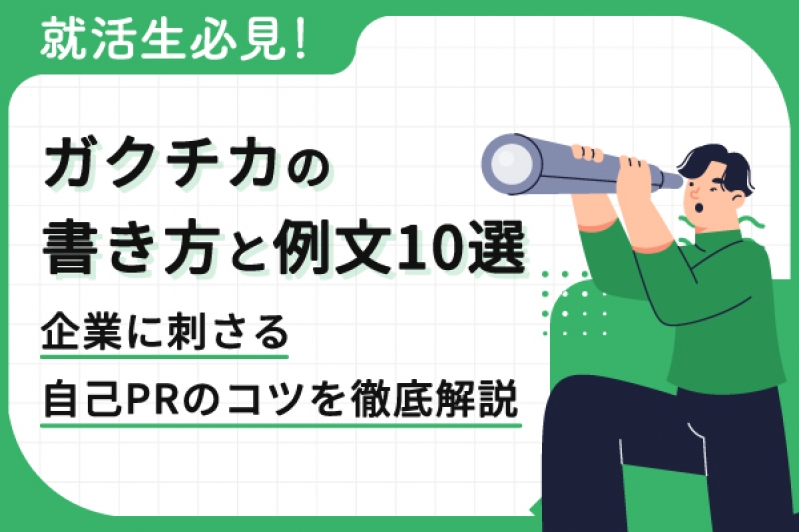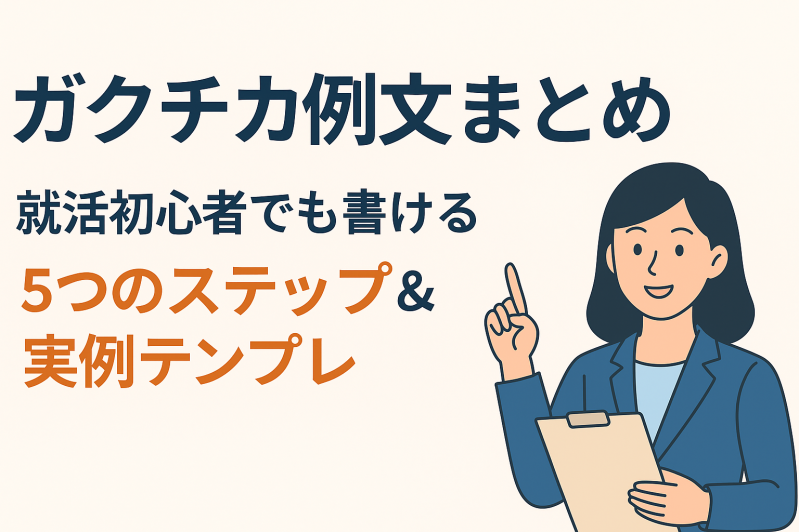【テーマ別例文つき】ガクチカの探し方や採用担当者に響く書き方を徹底解説
就職活動において、エントリーシート(ES)や面接で必ずと言っていいほど問われる「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)」
「ガクチカって、何を書けばいいか分からない…」
「アピールできるような、すごい経験なんてない…」
多くの学生が頭を悩ませる「ガクチカ」について、そう感じていませんか。
しかし、企業が見ているのは、すごい経験をしたかどうかではなく、その経験の中で「何を考え、どう行動したか」というプロセスなのです。
この記事では、ネタ探しの方法から、論理的な構成フレームワーク、そしてテーマ別の例文まで、ガクチカ作成の全プロセスを網羅的に解説します。
これを読めば、あなただけの強みが伝わる、採用担当者の心に響くガクチカが必ず書けるようになりますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
企業がガクチカで知りたい要素
企業がガクチカの質問を通して評価しようとしているのは、経験の華やかさではなく、その経験を通じて見えてくる学生の内面的な特性です。具体的には、以下の3つの要素を多角的に見極めようとしています 。
人柄・価値観
企業は、学生がどのようなことにモチベーションを感じ、どのような環境で能力を発揮する人物なのかを知りたいと考えています。
ガクチカのエピソードから学生の価値観や性格を読み取り、自社の社風やチームの文化に合致するかどうか、つまり「カルチャーフィット」を慎重に判断しているのです。
ミスマッチは、入社後の早期離職に繋がり、企業と学生双方にとって大きな損失となるため、これを避けることが採用活動の重要な目的の一つであるといえるでしょう。
思考力・課題解決能力
企業は、学生が困難な状況に直面した際に、どのように物事を捉え、課題の本質を分析し、解決策を立案し、そして行動に移すことができるのか、その一連の思考プロセスと行動特性を評価します。
ガクチカは、この課題解決能力を具体的に示すための絶好の機会であるといえます。単に「頑張った」という精神論ではなく、論理に基づいた行動が取れる人材かどうかが問われているのです。
何がモチベーションであるのか
「何がその学生を突き動かすのか」というモチベーションは、入社後のパフォーマンスを予測する上で非常に重要な指標です。
具体的には、
「誰かに与えられた目標に向かって頑張れるのか」
「人から感謝されることに喜びを感じる」
「自己の成長にやりがいを見出す」
といったことが挙げられます。
このモチベーションの源泉が、その企業の事業内容や仕事の進め方、評価制度と合致していれば、入社後も高い意欲を維持し、継続的に活躍してくれる可能性が高いと判断されるでしょう。
ガクチカの「ネタ」を探す上で重要なこと
ガクチカの題材は、学生生活のあらゆる場面に潜んでいます。重要なのは、経験の大小や成果の有無で、ネタが良いかどうか判断しないことです。
実績や成果の大小は重要ではない
採用担当者が最も重視するのは、結果そのものではなく、目標達成や課題解決に至るまでのプロセス(過程)です。
「困難に対してどのように考え、工夫し、行動したのか」という一連のプロセスにこそ、時分の人柄、価値観、能力が凝縮されているといえます。
したがって、「全国大会で優勝した」という輝かしい実績がなくても、「大会出場を目指して、チームの課題を分析し、練習方法を改善した」という過程を具体的に語れれば、それは十分に評価されるガクチカとなるのです。
一般的な経験で十分
アルバイト、サークル活動、部活動、ゼミ、研究、ボランティア、インターンシップなど、多くの学生が経験する活動は、すべてガクチカの優れた題材です。
そして、課題意識の持ち方や仕事への取り組み方は一人ひとり異なるため、他の学生と経験が似てしまうことに不安を感じる必要はありません。
重要なのは、そのありふれた経験の中で、自分自身が「何を考え、どう行動したか」というオリジナリティを語ることであるといえるでしょう。
ガクチカの基本構成
ガクチカの構成としては、以下の7つに分けることができます。この型に沿って自身の経験を整理することで、格段に論理的で分かりやすいガクチカになるでしょう。
① 結論
まず、何に力を入れたのかを簡潔に述べます。
「私が学生時代に最も力を入れたことは、〇〇サークルでの活動です。」のように、一文で明確に提示します。
② 動機
次に、なぜその活動に取り組もうと思ったのか、そのきっかけや背景を説明します。
「〇〇という課題意識があったため」「〇〇という目標に魅力を感じたため」など、あなたの価値観や主体性を示す部分です。
③ 目標と課題
その活動において、具体的にどのような目標を掲げたのか、そしてその目標達成の過程でどのような困難や課題に直面したのかを述べましょう。
目標は「売上を前月比15%向上させる」のように、可能な限り具体的に設定することが重要です。
④ 自身の行動・工夫
設定した目標の達成や、直面した課題の解決のために、あなたが具体的にどのような行動を取り、どのような工夫を凝らしたのかを述べます。
ここがガクチカの核となる部分であり、あなたの思考力や実行力が最も表れる箇所です。
⑤ 結果
あなたの行動の結果、状況がどのように変化し、どのような成果が得られたのかを具体的に示します。
ここでも「新入部員が5人から20人に増加した」のように、定量的であることを心がけましょう。
⑥ 学び
その一連の経験を通じて、何を学び、どのような能力が身についたのかを言語化します。
「この経験から、多様な意見を調整し、チームを一つの方向に導くことの重要性を学びました」といった形で述べるようにしましょう。
⑦ 入社後の貢献
最後に、その学びや経験を、志望する企業でどのように活かし、貢献していきたいかを述べて締めくくります。
これにより、企業はあなたの入社後の活躍を具体的にイメージすることができるのです。
テーマ別ガクチカ例文
この章では、就活生がガクチカのテーマとして選びやすい経験ごとに、例文を紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
アルバイト経験
アルバイトは、社会人としての働き方を具体的にイメージさせやすい、非常に強力なガクチカのテーマです。
単なる業務内容の報告ではなく、「自分ならではの課題意識」と「主体的な改善行動」を語ることが重要です。
【例文:飲食店の売上向上】(課題解決力・主体性のアピール)
私が学生時代に最も力を入れたことは、個人経営の居酒屋でのアルバイトにおいて、SNSを活用した新規顧客獲得です。
私が勤務していた店舗は、料理の評判は高いものの、路地裏という立地から新規顧客、特に若者層の来店が少ないという課題を抱えていました。
常連客に支えられている一方で、将来的な売上減少への危機感を店長と共有し、この状況を打開したいと考えました。
そこで私は、若者層へのアプローチとしてInstagramアカウントの開設と運用を店長に提案し、許可を得て担当しました。
まず、ターゲットである20代女性に響くよう、料理の写真を「シズル感」が伝わるように撮影・加工する工夫を凝らしました。
さらに、単なる情報発信に留まらず、「#〇〇(地名)グルメ」といったハッシュタグ分析を行い、近隣のグルメ好きユーザーにリーチできるよう努めました。また、来店時にInstagramへの投稿を促す割引キャンペーンを企画・実行し、UGC(ユーザー生成コンテンツ)による口コミの拡散を狙いました。
これらの施策を3ヶ月間継続した結果、フォロワー数は1,000人を超え、Instagram経由での新規来店客が月平均で約30組増加し、月の総売上は前年比で15%向上しました。
この経験から、現状を分析して課題を特定し、主体的に解決策を立案・実行することの重要性を学びました。
貴社においても、この課題解決能力を活かし、常に現状をより良くするための改善提案を行い、事業の成長に貢献したいと考えています。
サークル・部活動経験
サークルや部活動は、チーム内での役割遂行能力や目標達成意欲を示すのに適したテーマです。
重要なのは、「チームが〇〇を達成した」という集団の成果で終わらせず、その中で「自分がどのように貢献したか」という個人の役割を明確にすることであるといえます。
【例文:文化系サークルの参加率改善】(リーダーシップ・巻き込み力のアピール)
私が学生時代に力を入れたことは、所属していた映画研究サークルの活動活性化です。
私が2年次に幹部になった際、サークルの参加率は30%未満に低迷し、メンバー間の交流も希薄で、存続の危機にありました。
映画好きが集まったこの場所を、誰もが「居場所」と感じられる活気あるサークルにしたいという強い思いから、私は参加率を80%以上に引き上げることを目標に掲げました。
課題の原因は、活動が名作映画の鑑賞会に偏り、メンバーが受け身になっていたことだと考えました。
そこで私は、メンバーの主体性を引き出すために2つの施策を実行しました。
第一に、鑑賞会後に必ずグループディスカッションの時間を設け、各自の感想や解釈を共有する場を作りました。これにより、対話が生まれ、メンバー間の相互理解が深まりました。
第二に、「映画制作プロジェクト」を新たに企画し、脚本、監督、撮影、編集といった役割を全員に割り振り、一つの作品を共同で作り上げる経験を提供しました 。
当初は「面倒だ」という声もありましたが、各チームの進捗を共有する定例会を設け、私自身が率先して各チームの相談に乗ることで、徐々に一体感が醸成されました。
結果として、半年後にはサークルの平均参加率は85%に達し、完成した短編映画は大学の文化祭で上映され、最優秀賞を受賞しました。
この経験を通じて、明確なビジョンを掲げ、メンバー一人ひとりの主体性を引き出すことで、チーム全体の成果を最大化できるというリーダーシップの本質を学びました。
貴社でも、チームメンバーを巻き込みながら、困難なプロジェクトを成功に導いていきたいです。
ゼミ・研究・学業経験
学業に関するテーマは、論理的思考力、探求心、粘り強さといった、知的な誠実さをアピールするのに最適です。
ただし、専門的な内容に終始せず、その研究プロセスから得た汎用的なスキルを伝えることが重要であるといえます。
【例文:文系ゼミでの共同論文執筆】(分析力・協調性のアピール)
学生時代に最も力を注いだのは、〇〇経済学ゼミでの共同研究です。
私たちは「企業のダイバーシティ推進が組織パフォーマンスに与える影響」というテーマで論文を執筆しました。
当初、私たちのチームは先行研究のレビューに時間を要し、議論が発散してしまい、研究の方向性が定まらないという課題に直面しました。
私はこの状況を打開するため、まずメンバーの役割分担を明確にすることを提案しました。
具体的には、各々の興味関心に基づき、「女性活躍」「外国人雇用」「障がい者雇用」といったサブテーマを分担し、各自が責任を持って情報収集と分析を行う体制を整えました。
さらに、週に一度の定例会では、単に進捗を報告するだけでなく、各自の分析結果が全体の研究テーマにどう貢献するのかを議論する時間を設け、常に研究の全体像を共有するよう努めました。
この取り組みにより、研究効率が大幅に向上し、各メンバーの当事者意識も高まり、最終的に100社以上の企業データと従業員アンケートを統計的に分析し、「多様な人材が活躍できる心理的安全性の高い組織文化こそが、パフォーマンス向上の鍵である」という独自の結論を導き出しました。
この論文はゼミ内で高く評価され、学内の論文コンテストで優秀賞を受賞しました。
この経験から、複雑な課題に対して構造的にアプローチする分析力と、多様な意見を持つメンバーと協力して一つの目標を達成する協調性を学びました。
貴社においても、データに基づいた冷静な分析と、チームメンバーとの協力を通じて、課題解決に貢献できると確信しています。
ボランティア・インターンシップ経験
これらの経験は、社会との接点を持つ活動であり、職業観や働くことへの意欲を直接的に示すことができます。
特に、活動に参加した「動機」を明確に語ることで、あなたの価値観や社会貢献への意識を強く印象づけることができるでしょう。
【例文:長期インターンシップ】(実践的ビジネススキル・成長意欲のアピール)
私が学生時代に最も力を入れたことは、ITベンチャー企業での3ヶ月間の長期インターンシップです。
私がこのインターンに参加した動機は、大学で学んだマーケティング理論が、実際のビジネス現場でどのように通用するのかを肌で感じ、実践的なスキルを身につけたいと考えたからです。
そこでは、自社開発のタスク管理ツールの法人営業を担当しました。
当初、私はリストの上から順に電話をかけるだけの非効率な営業活動しかできず、アポイント獲得率は1%未満と、全く成果を出せずにいました。このままではチームに貢献できないという強い危機感を覚え、自分の行動を根本から見直しました。
まず、過去の成約事例を分析し、成約率の高い業界(IT、コンサルティング業界など)を特定しました。
次に、その業界の企業が抱えるであろう「プロジェクトの進捗管理」や「チーム内の情報共有」といった課題を仮説として立て、それに合わせたトークスクリプトを独自に作成しました。
この仮説検証型の営業アプローチに切り替えた結果、アポイント獲得率は5%まで向上し、最終的には3件の契約を獲得することができました。
この経験を通じて、単に行動量を増やすだけでなく、データに基づいた仮説を立て、効率的にアプローチすることの重要性を学びました。また、成果が出ない中でも諦めずに試行錯誤を続ける粘り強さも身につきました。
貴社に入社後も、この主体的な課題解決能力と粘り強さを活かし、高い目標にも果敢に挑戦していきたいです。
ガクチカを書く上での注意点
この章では、抽象的な表現を排除し、具体的で説得力のある文章を作成するための実践的なライティング技術を解説します。
これらの技術を駆使することで、ガクチカがより鮮明に、そして力強く相手の心に響くものとなるでしょう。
自己分析を徹底する
魅力的なエピソードを発掘するためには、過去の経験を体系的に整理し、深く掘り下げる自己分析が不可欠です。
自分史やモチベーショングラフなどを作成し、自分の強みが発揮された経験は何なのか、どのようなことにやりがいが喜びを感じるのかなどを、深く分析してみましょう。
一見些細なことでも、深く掘り下げていくことで、自分自身の軸や価値観が見えてくるため、ガクチカだけでなく、企業選びや自己PR、志望動機を語る上でも非常に重要になるので、しっかりと何度も行いましょう。
ーーーーーー
自己分析のやり方については、以下の記事で詳しく解説しております。
就活で必要不可欠な自己分析のやり方や注意点を徹底解説
企業の求める人物像を踏まえる
企業に刺さるガクチカを書くにあたって、まずは企業研究を行い、企業の求める人物像を理解することが重要です。企業HPやIR情報の確認、OB/OG訪問などを通して、業界研究とともに行うことで、その企業について深く理解することができるはずです。
そして、研究を通して見えてきた「求める人物像」に合ったアピールをすることが、ガクチカにおいて求められることであるといえます。
そのため、企業ごとに響きそうなエピソードを何個か用意をしたり、同じエピソードでも伝え方(アピールすること)を変えるなどの工夫が必要であるといえるでしょう。
ーーーーーー
企業研究のやり方については、以下の記事で詳しく解説しております。
企業研究の方法やメリット、選考で活かすためのポイントを徹底解説
「数字」と「固有名詞」の活用
説得力のあるガクチカでは、「具体性」が重要なポイントであるといえます。
そのため、曖昧で抽象的な表現ではなく、定量的表現を徹底することや、固有名詞でリアリティを出すことが重要であるといえるでしょう。
定量的表現においては、成果や努力の規模を具体的な数字で示すことで、エピソードのリアリティと説得力が飛躍的に向上します。
また、固有名詞でリアリティを出す点においては、具体的な名称を記述することで、話の信憑性が増し、採用担当者も状況をイメージしやすくなるでしょう。
アピールポイントは一貫する
一つのガクチカに「リーダーシップも、協調性も、課題解決能力もあります」と多くの強みを詰め込もうとすると、一つひとつのアピールが薄まり、結局どの強みも印象に残らないといった状況に陥る可能性があります。
最も伝えたいアピールポイント(強み)を一つに定め、エピソードのすべての要素(動機、課題、行動、結果、学び)がその強みを裏付けるように構成することが重要です。
これにより、一貫性のある力強いメッセージを伝えることができるでしょう。
まとめ
本記事では、ガクチカのネタ探しから構成の作り方、そして具体的な書き方のポイントまで、網羅的に解説しました。
最も重要なのは、繰り返しになりますが、経験の大小ではなく、その中で「何を考え、どう行動したか」というあなただけのプロセスです。
自己分析で自身の価値観を深く掘り下げ、伝わる文章構成や企業が求める人物像に沿って経験を語ることで、ありふれた経験でさえも、自分の強みをアピールできる強力なエピソードになるのです。
「書くことがない」と悩む必要はありません。必ずアピールできるエピソードがありますので、まずは自己分析を徹底的に行い、自分の強みが最大限に発揮されたプロセスを探してみましょう。