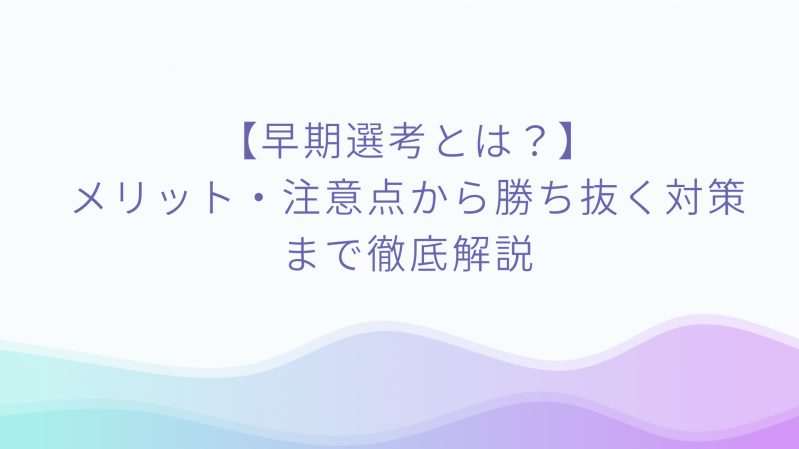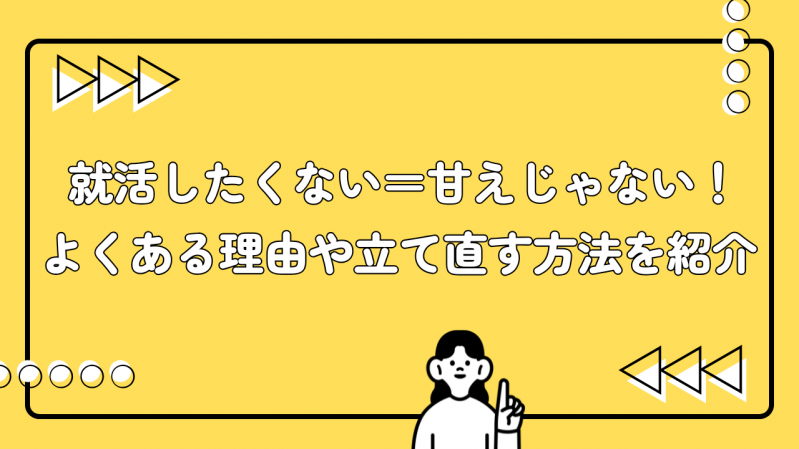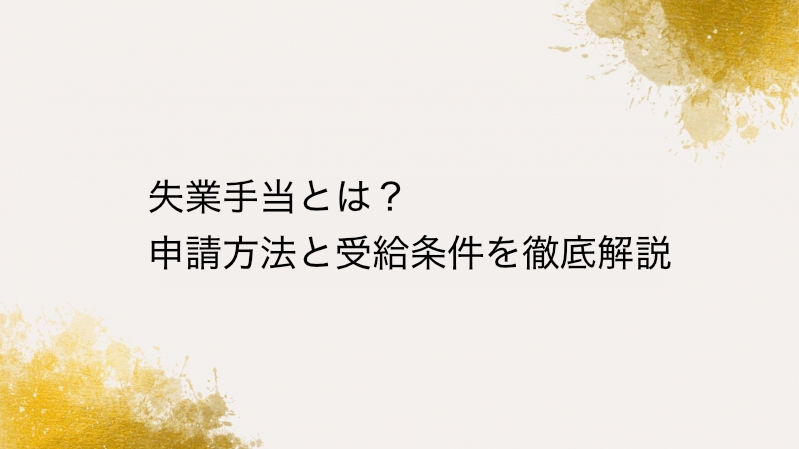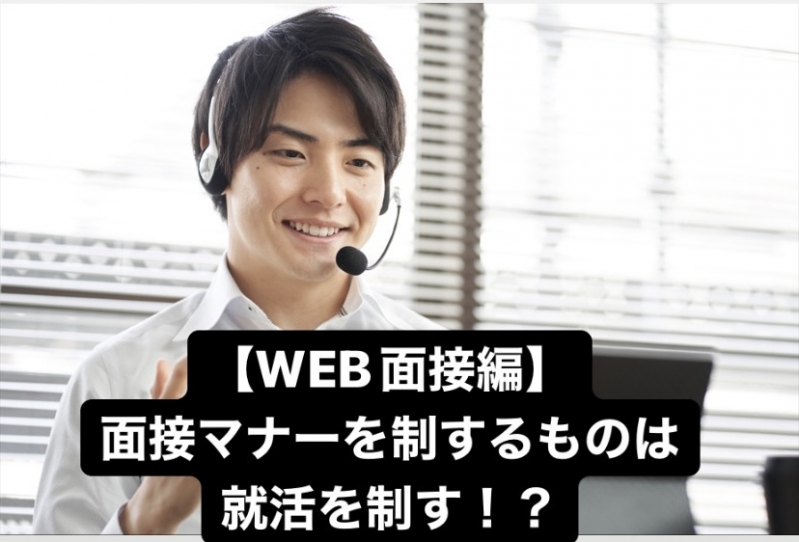【27卒】早期選考とは?メリット・注意点から勝ち抜く対策まで徹底解説
就職活動(以下、就活)という言葉を聞いて、何から始めればいいのか、周りはどう動いているのか、不安に感じていませんか?
特に近年、就活のスケジュールは大きく変化しており、「早期選考」という言葉を耳にする機会が増えたかもしれません。
この早期選考は、一部の学生だけが知る特別なルートではなく、今や多くの学生にとってキャリアを考える上で非常に重要な選択肢となっています。しかし、その実態や対策については、まだまだ知られていないことも多いのが現状です。
この記事では、就活を始めたばかりの人が、有利に進めるのに役立つ早期選考について完全に理解し、自信を持って活用できるよう、その基本から具体的な対策までを網羅的に解説します。
この記事を最後まで読めば、早期選考の全体像を掴み、自身の就活を戦略的に、そして有利に進めるための一歩を踏み出せるでしょう。
早期選考とは
早期選考とは、その名の通り、一般的な採用のスケジュールよりも早い時期に実施される選考のことを指します。
現在の就職活動には、政府が企業に要請している目安のスケジュールが存在します 。具体的には、以下の通りです。
〇広報活動開始: 卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降
〇採用選考活動開始: 卒業・修了年度の6月1日以降
〇正式な内定日: 卒業・修了年度の10月1日以降
しかし、上記はあくまで「要請」に過ぎず、特に外資系企業やベンチャー企業などは、このスケジュールに縛られずに採用活動を行うケースが多くなっています。
その結果、この「公式」スケジュールよりも数ヶ月、場合によっては1年近くも前倒しで選考が行われるのが「早期選考」の実態です。早いケースでは、大学3年生の春から夏にかけて選考が始まり、夏や秋には内々定が出ることも珍しくないのです。
企業はなぜ早期選考を行うのか?
では、なぜ企業はコストや手間をかけてまで、わざわざ選考スケジュールを前倒しにするのでしょうか。その背景には、企業側の明確な戦略と目的があります。
優秀な学生を早期確保したいから
企業が早期選考を実施する最も大きな理由は、ライバル企業に先駆けて優秀な人材を確保するためです。
就活が本格化する6月以降は、多くの学生が一斉に動き出すため、優秀な学生の奪い合いが激化します。企業は、その競争が始まる前に、自社が求める能力や価値観を持つ学生と接点を持ち、囲い込みたいと考えているのです。
特に、早くから就活を始めている学生は、行動力・意欲があり、自身のキャリアに対して真剣であると評価されやすく、企業にとって魅力的な存在となるでしょう。
志望度の高さを測る指標になるから
早期選考は、学生の志望度を測るための手段としても活用されています。
学生が時間と労力をかけて早期選考に参加すること自体が、その企業への高い関心や入社意欲の表れであると企業は判断します。
また、このような学生は、内定を出した場合の承諾率や、入社後の定着率が高い傾向にあります。さらに、早期選考に参加することで学生側も企業理解が深まり、企業と学生の双方にとってミスマッチを防げるのです。
入社前からの育成と関係構築
内定から入社までの期間が長くなることで、企業は「内定者インターンシップ」や懇親会などを通じて、学生との関係を深めることができます。
これにより、学生は入社前に企業文化や業務内容に慣れることができるでしょう。企業側も学生の適性をさらに詳しく評価し、入社後のスムーズな立ち上がりをサポートすることが可能になります。
このように、早期選考は単に「早い選考」というだけではありません。企業にとっては優秀な人材を確保するための戦略的な手段であり、学生にとっては自らの可能性を広げるチャンスとなる、双方にとって意味のある制度なのです。
早期選考のメリット
次に、早期選考に参加することで得られる大きなメリットを紹介します。
内定獲得による精神的な余裕を得られる
早期選考に参加する最大のメリットは、早い段階で内定を一つでも獲得することによる「精神的な安心感」です。
就職活動が本格化する中で「内定がない」状態は、大きな焦りや不安を生み、面接で本来の力を発揮できない原因になりがちです。
しかし、たとえ第一志望でなくとも、一つの内定が手元にあるだけで心に大きな余裕が生まれます。この余裕が自信となり、その後の第一志望の企業の選考にもリラックスして臨むことができるでしょう。
本選考の「練習」として経験を積める
早期選考は、就活の面接ならではの緊張感の中で選考プロセスを経験できる、またとない「練習の場」となります。
エントリーシートの作成から、グループディスカッション、そして企業の採用担当者と直接対峙する面接まで、一連の流れを実戦で学べる機会は非常に貴重です。
どんなに大学のキャリアセンターなどで模擬面接を重ねても、本物の選考でしか得られない独特の空気感やフィードバックがあります。
たとえ不採用という結果に終わったとしても、その経験を通じて自分の弱点や改善点を具体的に発見できれば、その後の本選考に向けた大きな糧となるでしょう。
選考フローが有利に進む可能性
選考フローが有利に進む可能性がある点も、早期選考に参加する大きなメリットです。
特に、企業のインターンシップやリクルーターとの面談などを経由して早期選考の案内を受けた場合、選考フローそのものが有利に進む可能性があります。
これらのルートでは、企業側はすでにある程度あなたの能力や人柄を評価しており、ポテンシャルを認めている状態からスタートします。
そのため、通常であれば必須となるエントリーシートの提出や一次面接、Webテストなどが免除されることがあります。選考ステップが短縮されれば、準備にかかる時間を節約できるだけでなく、精神的な負担も軽減できるでしょう。
早期選考における注意点
ここでは、早期選考における注意点を解説します。
優秀なライバルと競争する必要がある
早期選考は本選考よりも応募者の総数が少ないため、「競争率が低くて受かりやすい」と考えがちですが、これは大きな誤解です。
実際には、早くから行動する情報感度と意欲の高い学生が凝縮されているため、応募者一人ひとりのレベルは非常に高く、競争が激しい傾向にあります。
自己分析や企業研究といった準備が中途半端な状態で臨んでしまうと、優秀なライバルたちに圧倒され、まったく歯が立たないという事態に陥りかねません。
参加する上では、本選考と同様に覚悟を持って、万全の対策を講じる必要があるでしょう。
準備不足でチャンスを逃す可能性
選考の開始時期が早い早期選考において多くの学生が陥りがちなのが、「準備不足」という落とし穴です。
特に、自己分析や企業研究がまだ浅い段階で、「とりあえず受けてみよう」という軽い気持ちで挑戦してしまうケースがあります。
しかし、企業側も将来を担う優秀な人材を見極めようと真剣です。あなたの志望動機や自己PRが表面的であれば、その準備不足はすぐに見抜かれてしまいます。
結果として、本来であれば掴めたかもしれない貴重な内定のチャンスを逃すだけでなく、自信を大きく失う原因にもなりかねません。
早期選考への5つのルート
ここでは、早期選考につながる主要な5つのルートを紹介します。
インターンシップ
早期選考への最も主流なルートがインターンシップに参加することです。実際に、多くの企業が採用活動の一環としてインターンシップを位置づけています
企業は、数日〜数週間にわたるインターンシップを通して、学生のスキル、論理的思考力、チームワーク、人柄などを、実際の業務に近い環境でじっくりと評価します。
そして、そこで高いパフォーマンスを発揮した学生や、自社の文化に合うと判断された学生に対し、個別に早期選考の案内を送ります。
特に志望度の高い企業のインターンシップには、積極的に挑戦するようにしましょう。
スカウト・オファー型サイト
近年急速に普及しているのが、「逆求人サイト」とも呼ばれるスカウト・オファー型の就活サイトです。
これは、学生が自己PRやガクチカ(学生時代に力を入れたこと)、スキルなどを詳細にプロフィールとして登録しておくと、その内容に興味を持った企業側から「面談しませんか」「選考に参加しませんか」といったオファーが届く仕組みです。
企業を探す手間が省けるだけでなく、自分では見つけられなかった優良企業から早期選考のスカウトが来る可能性もあります。
このルートを有効活用するためには、企業の人事担当者の目に留まるよう、具体的で魅力的なプロフィールを書き込むことが重要です。
☞【最新版】スカウト特化の就活サイト6選!選び時のポイントについても解説
就活エージェント
就活エージェントは、キャリア相談やES添削、面接対策といったサポートを無料で提供してくれる民間の就職支援サービスです。
エージェントは、企業から非公開で採用依頼を受けている場合があり、一般には公開されていない早期選考の求人を紹介してくれることがあります。
自分一人では得られない情報にアクセスできるのが大きなメリットであるといえるでしょう。
また、求人の紹介・ES添削・面接対策など、就活のプロによるサポートを受けられるのも強みです。
☞【27卒】人気就活エージェントおすすめ7選!サービス毎の特徴やメリットをご紹介
OB・OG訪問
OB・OG訪問は、本来、その企業で働く先輩社員から仕事内容や社風についてリアルな話を聞き、企業研究を深めるための活動です。
しかし、訪問の場で自分の熱意や考えをしっかりと伝え、非常に良い印象を与えることができれば、訪問した社員が人事部に推薦してくれ、早期選考のきっかけとなるケースもあります 。
ただし、最初から選考への推薦を期待するような態度は相手に悪印象を与えかねないため、まずは純粋に「学びたい」という姿勢で臨むことが重要です。
☞OB・OG訪問とは?始めるタイミングやメリット・デメリット・探し方など詳しく解説!
企業HP・就活イベント
企業HPをチェックしたり、各種就活イベントに参加したりすることも、早期選考へのルートの一つです。招待を待つだけでなく、自ら積極的に情報を掴みに行く姿勢が大切なのです。
具体的には、志望企業の採用ホームページを定期的にチェックし、早期選考に関する情報が掲載されていないかを確認するとよいでしょう。
また、企業が合同で開催するキャリアイベントや、特定のテーマに沿った小規模な座談会などに参加すると、その場で人事担当者と直接話す機会が得られ、早期選考に招待されることもあります。
早期選考を勝ち抜くための対策
早期選考の切符を手に入れたとしても、そこで勝ち抜くことができなければ意味がありません。ここでは、そのための具体的な対策を解説します。
早期からの自己分析と企業研究を徹底する
早期選考の対策は、テクニック以前に、しっかりとした土台作りから始まります。
【自己分析】
なぜ働くのか、仕事を通じて何を成し遂げたいのか、自分の強みや価値観は何かといった「就活の軸」を明確にする作業が自己分析です。
本選考よりも早い段階で、自分の経験を深く掘り下げ、自分という人間を言語化しておく必要があります。
これが、説得力のある志望動機や自己PRを作成するための全ての材料となるでしょう。
【業界・企業研究】
なぜこの業界なのか、なぜ同業他社ではなくこの企業なのかという問いに明確に答えられなければ、高い評価は得られません。
企業の公式サイトを見るだけでなく、競合他社との違い、ビジネスモデル、業界内での立ち位置、そして今後の課題までを深く理解することが求められます。
この知識の深さが、他の学生との差別化に繋がります。
「ガクチカ」と自己PRを準備する
面接で必ずと言っていいほど聞かれるのが「学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)」です。
早期選考は大学3年生の早い段階で始まるため、アピールできる経験を積める期間が限られています。
そのため、大学1、2年生の頃から、サークル活動やアルバイト、インターンシップなど、何かに目標を持って主体的に取り組む経験を意識的に作っておくことが重要です。
そして、その経験から何を学び、それが企業でどう活かせるのか、一貫性のあるストーリーとして語れるように準備しておきましょう。
☞ES(エントリーシート)の正しい書き方とは?企業が見ているポイントも解説【例文つき】
筆記試験・Webテスト対策を講じる
選考フローが簡略化されることがあるとはいえ、多くの応募者を効率的に絞り込むために、SPIや玉手箱、GABといったWebテストや筆記試験が課されるケースは非常に多いです。
ここで基準点に達しなければ、面接に進むことさえできずに不合格となってしまいます。
志望企業がどの種類のテストを導入しているかを事前に調べ、市販の問題集やオンラインの模擬試験などを活用して、早い段階から対策を始めておきましょう。
☞【SPI対策】Webテストの種類や効率的な勉強方法を徹底解説!
面接対策を入念に実施する
早期選考の面接は、準備万端の優秀な学生が相手となるため、より高いレベルの受け答えが求められます。内容はもちろんのこと、自信のある立ち居振る舞いや、明確で論理的な話し方も重要です。
大学のキャリアセンターや就活エージェントなどを利用し、模擬面接を繰り返し行いましょう。客観的なフィードバックをもらうことで、自分では気づかない癖や改善点を修正できます。
緊張するのは当たり前です。緊張した状態でも、練習してきたことをしっかりと話せるようになるまで、場数を踏むことが成功の鍵です。
☞【27卒必見】面接を成功させるための準備から実践まで徹底解説
早期選考に関するQ&A
最後に、多くの学生が抱く早期選考に関する疑問について、Q&A形式でお答えします。
Q1: 早期選考に落ちたら、本選考でもう一度受けられますか?
A: 早期選考に落ちても本選考を受けられるかは、企業の方針によって全く異なります。
早期選考で不合格になっても、本選考に再チャレンジできる企業もあれば、「選考への応募は1度きり」と定め、再応募を認めていない企業もあります。
最も確実な方法は、企業の採用サイトに掲載されている募集要項を注意深く確認することです。そこに明記されていない場合は、人事部に直接、失礼のないように問い合わせてみるのも一つの手です。
もし再応募が可能な場合でも、なぜ早期選考で落ちたのかを徹底的に分析し、ESや面接内容を大幅に改善しなければ、同じ結果を繰り返す恐れがあるため、注意しましょう。
Q2: 早期選考の内定は辞退できますか?
A: 早期選考の内定を辞退することは、全く問題ありません。
企業から提示される「内々定」には法的な拘束力はなく、学生は承諾・辞退を自由に選べます。
もし辞退を決めた場合は、社会人としてのマナーとして、できるだけ早く電話やメールで丁寧に連絡することが重要です。まずは内定をいただいたことへの感謝を伝え、その上で辞退の意思を明確に伝えましょう。
まだ他の企業と比較検討中で迷っている場合は、正直にその旨を伝え、いつまでに返事をするか、回答期限を相談することも可能です。
Q3: 準備不足だと感じます。それでも挑戦すべきでしょうか?
A: 基本的には「挑戦すべき」と言えます。
たとえ不合格だったとしても、本番の選考を経験すること自体が、その後の就職活動において非常に貴重な財産になるからです。最高の面接練習の場と捉えることもできます。
ただし、第一志望群の企業で、かつ「再応募不可」のルールがある場合は、慎重な判断が必要です。挑戦するのであれば、後悔しないためにもしっかりと準備をした上で臨みましょう。
まとめ
この記事では、一般的なスケジュールより早く実施される「早期選考」について、その全体像を解説しました。
早期選考は、企業にとっては優秀な学生を早期に確保する目的があります。また、学生にとっては、早い段階で内定を得ることで精神的な余裕が生まれたり、本選考の絶好の練習になったりする大きなメリットがあります。
一方で、準備万端なレベルの高い学生が集まるため、生半可な対策では通用しないという注意点も存在します。
早期選考へは、インターンシップやスカウト型サイト、OB・OG訪問など、多様なルートから参加可能です。
早期選考を上手に活用するには、大学の早い段階からの自己分析や企業研究、ガクチカの準備、そして筆記試験や面接の対策が不可欠です。
早期選考の仕組みを正しく理解し、戦略的に準備を進めることが、自身のキャリアを有利に切り拓くための重要な鍵となるでしょう。