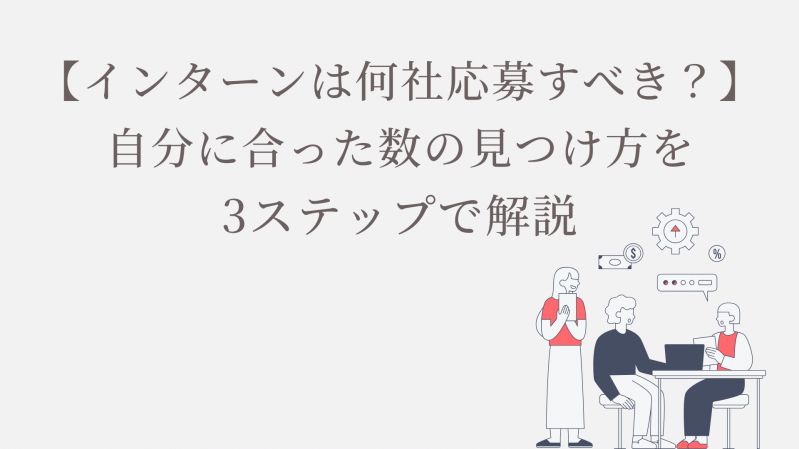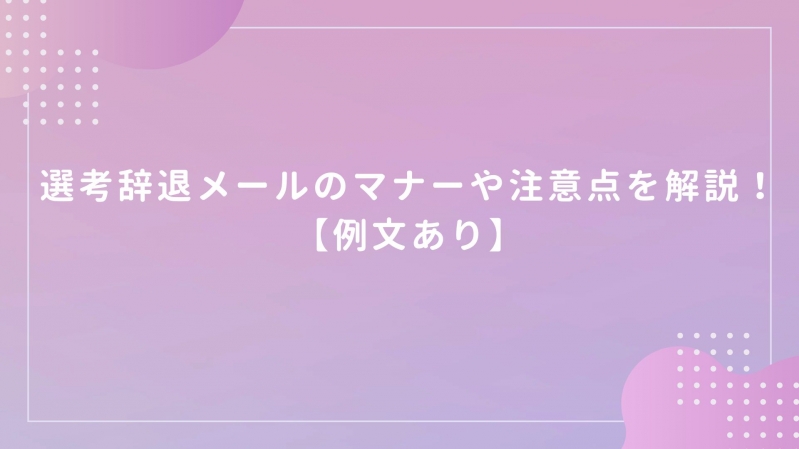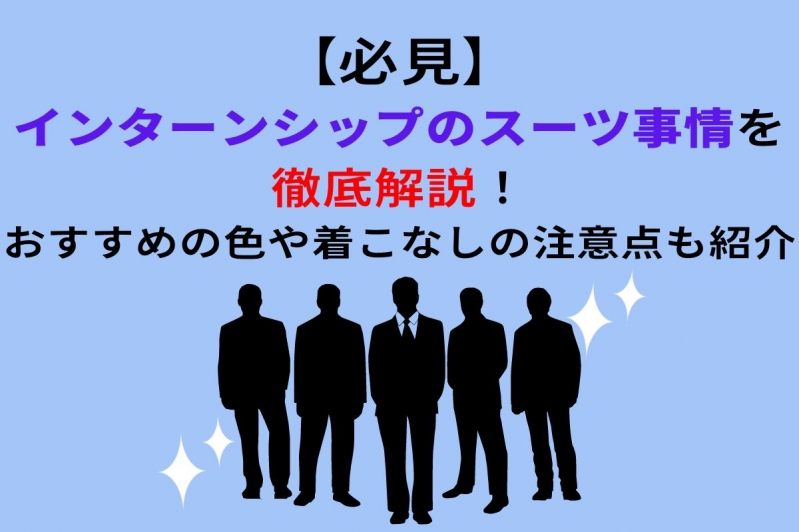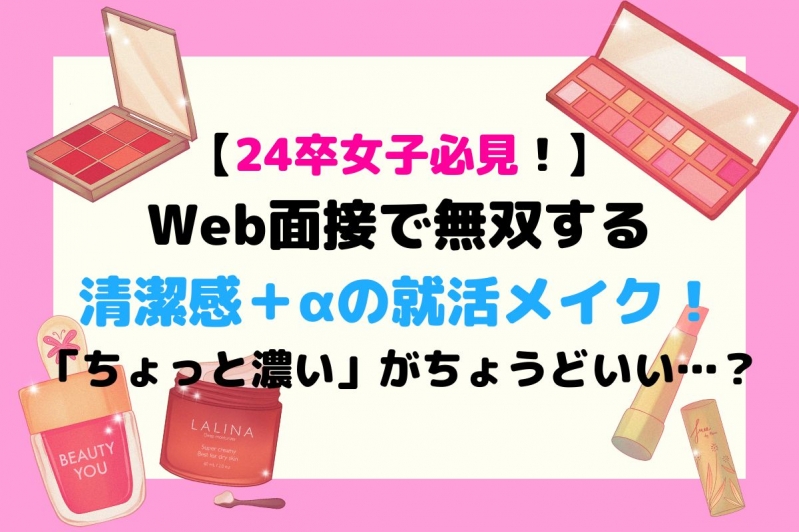【インターンは何社応募すべき?】自分に合った数の見つけ方を3ステップで解説
インターンシップの募集が始まり、
「一体何社くらい応募するのが普通なんだろうか?」
「多すぎても対策が雑になるし、少なすぎても全滅が怖い…」
といった不安を抱えている就活生は多いと思います。
この記事では、「平均〇社」という答えではなく、あなた自身の目標や状況に合わせて「最適な応募社数」を導き出すための具体的な考え方をご紹介します。
まずは一般的な応募社数のデータを確認した上で、「目標」「時間」「戦略」という3つの視点から、応募する計画を立てる方法を解説していきますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
平均応募社数は?
まず気になるのは、「他の学生は一体何社くらい応募しているのか」という点でしょう。世の中の就活生がどの程度応募しているのか、客観的なデータから見ていきましょう。
ただし、ここで重要なのは、データを鵜呑みにせず、あくまで自分自身の状況を考えるための「一つの材料」として捉えることです。
一般的なデータの提示
各種就活情報サイトの調査データを見ると、インターンシップへの応募社数は、平均して10社から20社程度となっています。
もちろん、これはあくまで平均値であり、中には30社以上に応募する学生もいれば、5社程度に絞って応募する学生もいます。
特に、サマーインターンなど、多くの企業が一斉に募集を開始する時期には、応募社数が多くなる傾向が見られます。
この数字を見て、「思ったより多いな」と感じるか、「意外と少ないな」と感じるかは人それぞれでしょう。
大切なのは、この平均値に自分が合わせるのではなく、この数字を参考にしながら自分の戦略を立てることです。
データはあくまで「参考値」
平均10社〜20社というデータは、あくまで様々な学生の平均値に過ぎません。
例えば、幅広い業界に興味がある文系の学生と、専門分野がある程度定まっている理系の学生とでは、おのずと応募社数は変わってきます。
また、人気が高く選考倍率の高いコンサルティング業界や総合商社を志望する場合は、自然と応募社数を増やさなければ参加のチャンスを得にくいかもしれません。
そして、自身の性格や学業の忙しさ、就活にかけられる時間といった個人のキャパシティによっても、「適切」な数は大きく異なります。
「平均が20社だから自分も20社応募しよう」と考えるのではなく、なぜその数なのか、自分にとってはどうなのか、という視点を持つことが、後悔しないインターン選びをする上で重要です。
【目標設定】あなたはなぜインターンに参加するのか?
自分に合った応募社数を見つける上で最も重要なのが、「インターンに参加する目的」を明確にすることです。目的がはっきりすれば、おのずと応募すべき企業の数や種類が見えてきます。
ここでは、目的を3つのタイプに分け、それぞれの応募社数の目安をご紹介します。
① 業界・職種探求タイプ(視野を広げたい)
まだ特定の業界や職種に強いこだわりがなく、「世の中にどんな仕事があるのか広く知りたい」「自分の興味の方向性を探りたい」と考えているという場合は、このタイプに当てはまります。
この場合、応募社数は15社以上と多めに設定するのがおすすめです。
IT、メーカー、金融、広告など、あえて異なる業界のインターンに複数応募し、実際に参加して比較検討することで、それぞれの業界の雰囲気や仕事内容の違いを肌で感じることができます。
様々な企業のプログラムに触れる中で、今まで知らなかった魅力的な企業に出会えたり、逆に「この業界は自分には合わないかも」といった気づきを得られたりします。
多くの選択肢に触れることが、納得のいくキャリア選択に繋がるでしょう。
② 志望業界・企業絞り込みタイプ(特定の分野に興味がある)
「IT業界には興味があるけど、どの企業が良いか分からない」「メーカーで働きたいけど、BtoBとBtoCの違いを知りたい」など、ある程度興味のある分野が定まっているという場合は、このタイプに当てはまります。
この場合の応募社数は10社前後が目安となるでしょう。
興味のある業界の中で、事業内容や企業規模が異なる複数の企業に応募するのが効果的です。
例えば、同じIT業界でも、大手のSIer、急成長中のWeb系ベンチャー、外資系のソフトウェア企業などに応募することで、社風や働き方の違いを深く理解できます。
一つの業界を多角的に見ることで、企業選びの軸がより明確になり、志望動機にも深みが増すでしょう。
③ 特定企業狙い撃ちタイプ(第一志望が明確)
すでに入社したい第一志望の企業が明確に決まっている場合は、このタイプに当てはまります。
その企業への熱意が非常に高い場合、応募社数は5社程度と少数に絞るとよいでしょう。
応募数を絞ることで、一社一社に十分な時間をかけ、徹底的な企業研究や質の高いエントリーシート(ES)作成、面接対策に集中できます。
その企業がなぜ好きなのか、入社して何を成し遂げたいのかを深く掘り下げ、熱意を余すことなく伝えましょう。
ただし、このタイプは不合格だった場合のリスクが大きいことも忘れてはいけません。万が一に備え、第一志望の企業と事業内容や社風が似ている企業をいくつかリストアップし、併願しておくようにしましょう。
【時間管理】質と量のバランスを見極める
インターンに応募する上で、やみくもに数を増やすのは得策ではありません。大切なのは、自分自身がかけられる時間と労力を正しく見積もり、一社一社の選考に丁寧に取り組むことです。
「応募できる数」と「対策できる数」は違う
エントリーボタンを押すだけなら、1日に何十社でも応募できるかもしれませんが、インターンの選考を突破するためには、企業研究、ES作成、Webテスト対策、面接準備など、多大な時間と労力が必要です。
例えば、質の低いESを100社に送るよりも、企業の心に響くよう魂を込めて書いたESを10社に送る方が、結果的にインターン参加に繋がる可能性は遥かに高いでしょう。
一社一社に対して「なぜこの会社でなければならないのか」を自分の言葉で語れるレベルまで準備することが、内定への近道です。
数打てば当たるといった考えは捨て、質を重視するようにしましょう。
自分のキャパシティを考えてみる
自分は一体何社なら質の高い対策ができるのか、一度自分のキャパシティを客観的に計算してみましょう。
例えば、1社応募するために必要な時間を「企業研究2時間、ES作成3時間」の合計5時間と仮定します。もし1週間に就活に使える時間が15時間だとすれば、単純計算で週に3社、1ヶ月で約12社が質の高い対策ができる上限となります。
もちろん、これはあくまで一例であり、大学の授業やゼミ、アルバイト、サークル活動などとのバランスを考えることが非常に重要です。
無理なスケジュールを立てて全てが中途半端になるよりも、現実的に可能な範囲で着実に進める方が、メンタル的にも安定し、良い結果に繋がるでしょう。
【戦略立案】応募企業のポートフォリオを組む
「応募した企業に全滅してしまった」「本命企業の選考までに一度も面接を経験できなかった」といった事態を避けるためには、応募する企業の「ポートフォリオ」を組むことが重要です。
自分の興味や選考の難易度に応じて、応募先をバランス良く配分しましょう。
① 本命企業(3割)
ポートフォリオの中核をなすのが、「第一志望群」である本命企業です。
これは、心の底から「この企業で働きたい!」と思える、最も熱意のある企業群を指します。全応募社数のうち、約3割をこのカテゴリに割り当てましょう。
これらの企業に対しては、他のどの企業よりも時間をかけて、徹底的に対策を行います。
企業のIR情報(投資家向け情報)を読み込んだり、OB・OG訪問をしたりと、使える手段は全て使って情報を集め、ESや面接で他の学生との圧倒的な差を見せつけましょう。
※企業研究やOB・OG訪問については、以下の記事で詳細に説明しておりますので、ぜひご覧ください。
☞企業研究の方法やメリット、選考で活かすためのポイントを徹底解説
☞OB・OG訪問とは?始めるタイミングやメリット・デメリット・探し方など詳しく解説!
② 挑戦企業(4割)
次に、全体の約4割を占めるのが「挑戦企業」です。
これは、現時点での自分の実力からすると少し難易度が高いと感じるものの、非常に魅力的に感じる企業群を指します。業界のリーディングカンパニーや、非常に人気が高く倍率の高い企業などがこれにあたります。
挑戦企業の選考を受ける目的は、自分の実力を試し、ハイレベルな選考プロセスを経験することにあります。
たとえ結果が不合格だったとしても、優秀な学生たちと議論を交わしたり、レベルの高いフィードバックをもらえたりする経験は、自身を大きく成長させ、本命企業の選考に活きてくるといえるでしょう。
③ 練習・滑り止め企業(3割)
そして、残りの3割は「練習・滑り止め企業」です。このカテゴリの目的は、大きく二つあります。
一つは、ESや面接といった選考プロセスそのものに慣れるという目的です。
本命企業の選考をぶっつけ本番で迎えるのは非常に危険であるため、面接の緊張感や独特の雰囲気を事前に経験しておくことで、本番で落ち着いて実力を発揮できるようになります。
もう一つの目的は、「最低でも1社はインターンに参加できる」という安心感を得ることです。
手元に一つの合格があるだけで、精神的な余裕が生まれ、その後の挑戦的な就職活動を支える土台となるでしょう。
まとめ
インターンの最適な応募社数に、正解は存在しません。最も重要なのは、周りの学生の数に惑わされることなく、自分自身の「目的」を明確にし、使える「時間」と相談しながら、戦略的な「ポートフォリオ」を組むことです。
なぜインターンに参加するのか、そのためにどれくらいの時間を割けるのか、そして、どのような企業に挑戦したいのかという3つの問いに真剣に向き合うことが、後悔のない選択に繋がります。
まずは、この記事で紹介した3つのSTEPを参考に、ぜひ自分だけの応募計画を立ててみましょう。