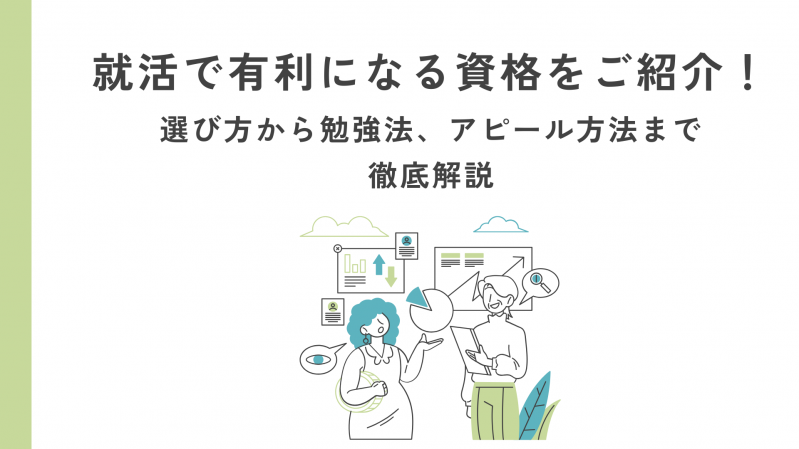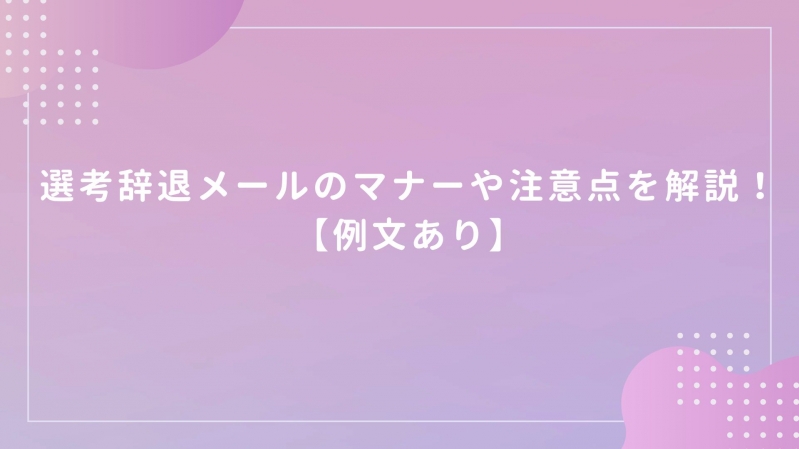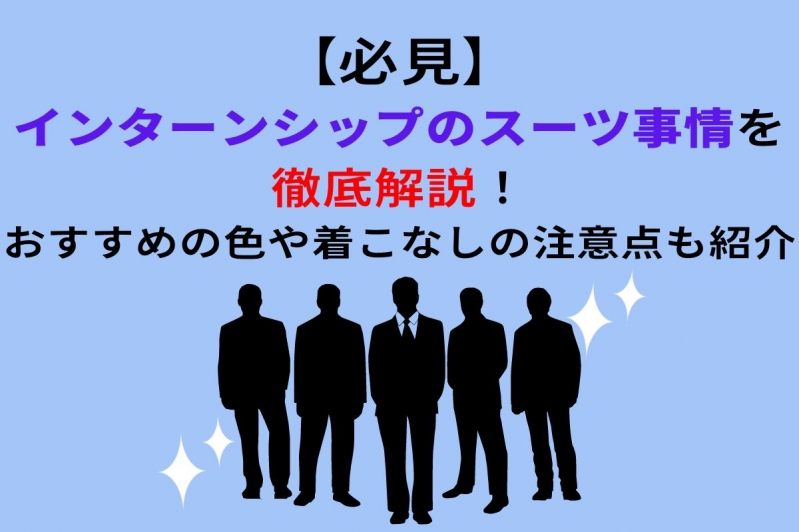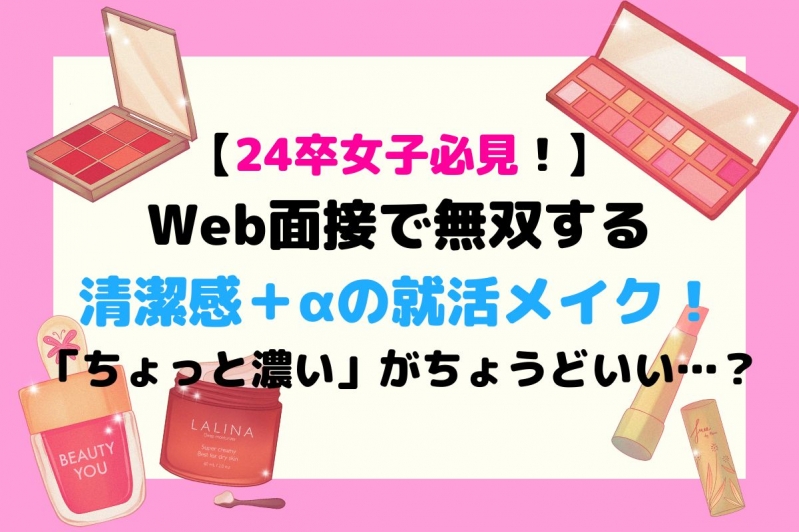就活で有利になる資格をご紹介!選び方から勉強法、アピール方法まで徹底解説
「周りのみんなが資格を取り始めて焦る…」
「就活のために、何か資格を取ったほうがいいのかな?」
就職活動を意識し始めると、多くの学生がこのような不安を感じるかもしれません。
就活において資格は「必須」ではありません。しかし、志望業界や職種に合った資格を取得していれば、選考で大きくアピールすることができるでしょう。
この記事では、就活における資格の本当の価値から、後悔しない選び方、業界別のおすすめ資格、最適な勉強法、そして面接官に響く自己PR術まで、すべてを分かりやすく解説します。
そもそも、就活に資格は必要なのか
まず大切なのは、資格を持っていないからといって選考で不利になることはない、ということです。
企業が採用で最も重視するのは、現時点でのスキルよりも、これからの「成長力」や「意欲」といった部分であるからです。
では、なぜ資格が有利に働くことがあるのでしょうか。それは、資格そのものよりも、「なぜ、どのようにしてその資格を取得したのか」というプロセスが、あなたのポテンシャルを客観的に証明してくれるからです。
企業は、資格取得のプロセスから、以下のような学生の強みを読み取っています。
〇熱意
志望する業界に関連する資格を持っていれば、その業界への関心の高さや本気度を具体的に示すことができます。
〇計画性
大学の授業やアルバイトと両立しながら、目標を立てて計画的に勉強し、合格という結果を出した経験は、社会人に不可欠な目標達成能力や自己管理能力の高さをアピールする格好の材料になります。
〇専門知識
資格は、その分野に関する一定レベルの知識を持っていることの客観的な証明です。企業にとっては、早期に戦力になってくれる人材として魅力的に映ります。
多くの学生が自己PRで「サークル活動で頑張った」「アルバイトで継続力を培った」といったエピソードを語りますが、面接官はその話を客観的に検証できません。
しかし、資格取得という経験は、目標設定から計画、努力、そして結果という一連のプロセスを、誰もが納得できる形で示すことができるため、資格取得のストーリーは非常に信頼性の高い「ガクチカ」になるのです。
後悔しない資格の選び方
資格を取るなら、自分のアピールにつながるものを選ばなければ意味がありません。資格選びのプロセスは、それ自体が「自分は将来どうなりたいのか」を考える自己分析の機会でもあります。
なぜその資格を選んだのか、その選択の背景まで語れるような、後悔しないための3つの選び方をご紹介します。
行きたい業界・やりたい仕事から選ぶ
自分のキャリアプランと関連性のない資格をアピールしても、面接官は「なぜうちの会社に?」と疑問に思うだけです。
例えば、IT企業を目指すならITパスポート、不動産業界なら宅地建物取引士(宅建士)というように、志望業界で直接役立つ資格を選ぶことが、熱意を伝える上で最も効果的であるといえるでしょう。
「なぜ?」を語れる資格を選ぶ
「就活に有利そうだから」という理由だけで取得した資格は、まず評価されません。
なぜその資格に興味を持ったのか、自分のどんな目標や夢につながっているのかを具体的に語れることが重要です。
「将来、海外で活躍したいという夢を実現するため、まずはビジネス英語の基礎力を客観的に証明しようとTOEICの勉強に励みました」といったストーリーがあれば、自分の価値観や人柄を伝えることができ、立派な自己PRとなるでしょう。
迷ったら「どこでも使える」汎用性の高い資格を選ぶ
まだやりたい仕事が明確に決まっていない学生も多いでしょう。この場合は、どのような業界・職種でも評価されやすい「汎用性の高い資格」を取得するのがおすすめです。
資格取得に向けた勉強を通して、ビジネスパーソンとしての基礎的なスキルを身につけることができ、将来の選択肢を狭めることなく、自分の可能性を広げることができるでしょう。
どのような業界でも役立つ資格6選
「どの資格を取ればいいか分からない」という人のために、どのような企業でも評価されやすい、汎用性の高い資格を6つ厳選してご紹介します。
〇TOEIC
ビジネス英語の能力を測る世界共通のテストです。
グローバル化が進む現代において、多くの企業が社員の英語力を重視しており、スコアで客観的に英語力を証明できるTOEICは非常に価値が高いといえます。
業界や企業によりますが、履歴書に書くなら最低でも600点以上、アピールするなら700点以上を目指すようにしましょう。
〇日商簿記検定
企業の経営成績や財政状態を読み解くための会計スキルを証明する資格です。
経理職だけでなく、営業職や企画職など、あらゆる職種で役立つ「ビジネスの共通言語」であるといえます。
就活でアピールするなら2級の取得が一般的ですが、まずは3級から挑戦するのも良いでしょう。
〇ITパスポート
ITに関する基礎知識を証明する国家資格です。
今やどんな業界でもIT活用は必須であり、この資格を持っていることで、ITリテラシーの基礎があることをアピールできます。
エンジニア志望者だけでなく、文系の学生にも強くおすすめできる資格であるといえるでしょう。
〇MOS (マイクロソフト オフィス スペシャリスト)
WordやExcel、PowerPointといった、仕事で毎日使うツールの操作スキルを証明する国際資格です。
特に事務職や営業職では、資料作成やデータ分析の効率に直結するため、即戦力として評価されやすい資格であるといえます。
〇普通自動車免許
見落としがちですが、これも履歴書に書ける立派な資格です。
特に営業職や地方勤務の可能性がある企業では、入社までに取得を求められるケースも少なくありません。
〇秘書検定
正しい敬語の使い方、電話応対、ビジネス文書の作成といった、社会人としての基本的なビジネスマナーが身についていることを証明できます。
秘書を目指す人だけでなく、あらゆる職種で求められる「社会人基礎力」のアピールになります。履歴書には2級以上から記載するのが一般的であるといえるでしょう。
【汎用資格6選早見表】
専門性をアピールできる業界別おすすめ資格
すでに行きたい業界が決まっているなら、より専門性の高い資格でライバルに差をつけましょう。ここでは、業界別におすすめの資格をご紹介します。
【金融・不動産・建設業界】
〇宅地建物取引士 (宅建士)
不動産業界では必須ともいえる国家資格です。
宅建士にしかできない「独占業務」があるため、非常に価値が高く、不動産を担保に融資を行う金融業界や、自社物件を販売する建設業界でも高く評価されています。
学生のうちに取得していれば、入社意欲の強烈なアピールになるでしょう。
〇FP (ファイナンシャル・プランニング) 技能士
税金、保険、年金、資産運用など、お金に関する幅広い知識を証明できます。
金融業界や保険業界を目指すならぜひ取得したい資格です。
〇証券外務員
銀行や証券会社で金融商品を販売するために必須の資格です。
入社後に取得が義務付けられることが多い資格ですが、先に持っていると選考で有利になる可能性があるといえます。
【IT・Web業界】
〇基本情報技術者試験
ITエンジニアの登竜門とされる国家資格です。
ITパスポートより一歩進んだ、技術的な知識とスキルを体系的に証明できる資格となっています。
〇応用情報技術者試験
ITを活用したサービス、製品、システムの開発や運用に関する知識と技能を測る試験です。
より高度な知識と応用力をアピールでき、学生で持っていると評価が非常に高くなるでしょう。
〇その他専門資格
データベース関連の「オラクルマスター」、ネットワーク関連の「CCNA」など、特定の分野に特化した資格は、より深い専門性を示したい場合に有効であるといえるでしょう。
【商社・メーカー】
〇高スコアのTOEIC/TOEFL
総合商社やグローバルメーカーでは、高い英語力が求められます。
TOEICなら730点以上、企業によっては800点以上が目安になることもあります。
〇通関士
輸出入の手続きを行うための国家資格です。
貿易に関わる商社やメーカーの物流部門で重宝されるでしょう。
〇危険物取扱者
化学薬品や石油などを扱う化学・化粧品・食品メーカーなどで必要とされる資格です。
【小売・サービス】
〇登録販売者
ドラッグストアなどで一般用医薬品(第2類・第3類)を販売できる専門資格です。
小売業界でのニーズが非常に高いといえるでしょう。
〇販売士
マーケティングや店舗運営の知識を証明する資格で、小売業界全般で役立ちます。
資格はいつ取ればよいのか?
資格を取る最適なタイミングは、大学2年生であるといえます。
大学1年生は新しい環境に慣れるので精一杯、3年生になるとインターンシップや自己分析で本格的に就活が始まり、勉強に集中する時間はなかなか取れません。
そのため、比較的授業にも慣れて時間に余裕が生まれる2年生が、資格の勉強に集中できる時期なのです。
そして、大学3年生の夏から始まるサマーインターンシップの選考でアピールするためには、それまでに資格を取得しておくのが理想です。早めに資格を取得することは、単に履歴書に書ける項目が増える以上の意味を持ちます。
それは、2年生のうちに資格を手に入れることで、自信を持って3年生からのインターンシップ選考に臨むことができ、質の高いインターンシップに参加できれば、それがまた新たな自己PRの材料となり、本選考をさらに有利に進められるという「好循環」が生まれるのです。
学習方法について
資格取得を目指すには、主に「独学」「通信講座」「専門学校(予備校)」の3つの方法があります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分に合った方法を選びましょう。
【学習方法メリット・デメリット比較】
資格を武器にする自己PRの書き方について
事実だけでなく、ストーリーを語る
「日商簿記2級を取得しました」という事実だけをただ履歴書に書くだけでは、あなたの魅力は伝わりません。
「なぜその資格を取ろうと思ったのか」「目標達成のためにどんな工夫や努力をしたのか」というストーリーを語ることで、人柄や強みをアピールできます。
自己PRは、以下の構成で組み立てるのがおすすめです。
①結論(自分の強み)
資格取得の経験を通じてアピールしたい強みを最初に述べる
②具体的なエピソード(資格取得のプロセス)
強みを裏付けるために、目標設定、計画、行動、困難を乗り越えた工夫などを具体的に述べる
③入社後の貢献
その強みを、入社後にどう活かしていきたいかを述べる
自己PRの例文
以下では、資格取得を活かした自己PRの例文を2つご紹介します。
〇「計画性」を日商簿記でアピールする例文
私の強みは、目標達成に向けて計画的に行動できることです。
大学の講義で企業の財務分析に興味を持ち、会計の知識を体系的に学びたいと考え、日商簿記検定2級の取得を決意しました。
大学の授業やアルバイトと両立するため、半後の試験日から逆算して学習計画表を作成し、毎日2時間の勉強時間を確保するため、通学電車ではスマートフォンのアプリで仕訳問題を、帰宅後1時間で参考書を読む、というルールを徹底しました。
その結果、計画通りに学習を進め、一度の受験で合格することができました。
この計画実行力を、貴社での業務においても、着実に目標を達成するために活かしていきたいと考えております。
〇「向上心」をTOEICでアピールする例文
私の強みは、常に高みを目指す向上心です。
将来グローバルな舞台で活躍したいという目標があり、その第一歩としてTOEICのスコアアップに挑戦しました。
初めて受験した際のスコアは500点でしたが、悔しさをバネに「850点以上」という目標を掲げ、毎日2時間の学習に加え、参考書だけでは学べない実践的な会話力を養うため、留学生との交流サークルにも参加しました。
その結果、3回目の受験で850点を取得することができました。
現状に満足せず、今も目標の900点を目指して学習を続けています。貴社に入社後は、この向上心と英語力を活かし、海外事業の拡大に貢献したいです。
履歴書への書き方
資格は、正式名称で、取得した年月とともに正確に記載しましょう。
〇普通自動車第一種運転免許 取得 (20XX年XX月)
〇日商簿記検定試験2級 合格 (20XX年XX月)
〇TOEIC Listening & Reading Test 850点 取得 (20XX年XX月)
〇ITパスポート試験 合格 (20XX年XX月)
まとめ
就活における資格は、自分自身の努力や熱意、計画性を客観的に証明し、自信を与えてくれる強力な「武器」であり、未来の可能性を広げるものであるといえます。
大切なのは、資格取得のプロセスで得た「ストーリー」を語ること、自分の目標から逆算して戦略的に資格を選ぶこと、時間に余裕のある大学2年生のうちに行動を起こすことであるといえます。
この記事を参考に、就活に向けて自分の武器となる資格を手に入れ、自信を持って就職活動に臨んでください。