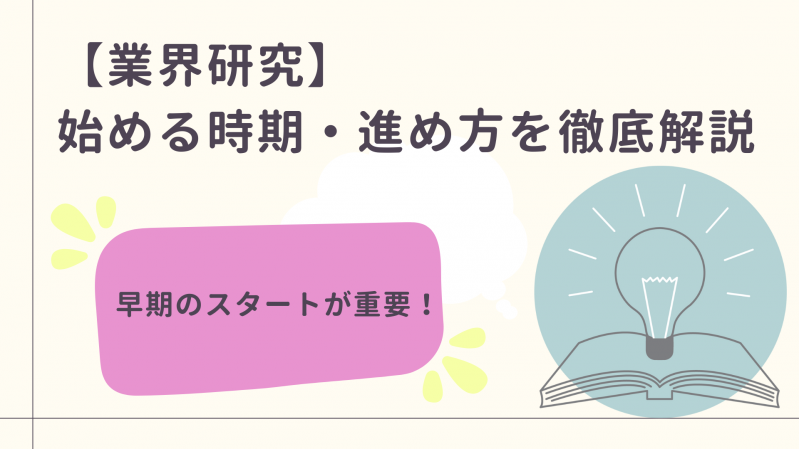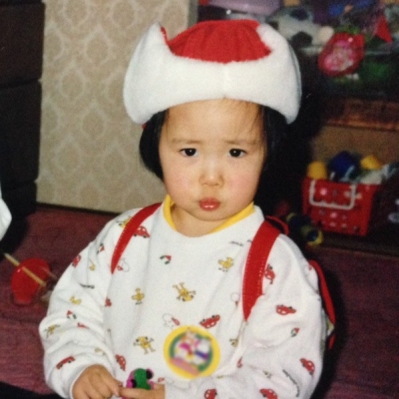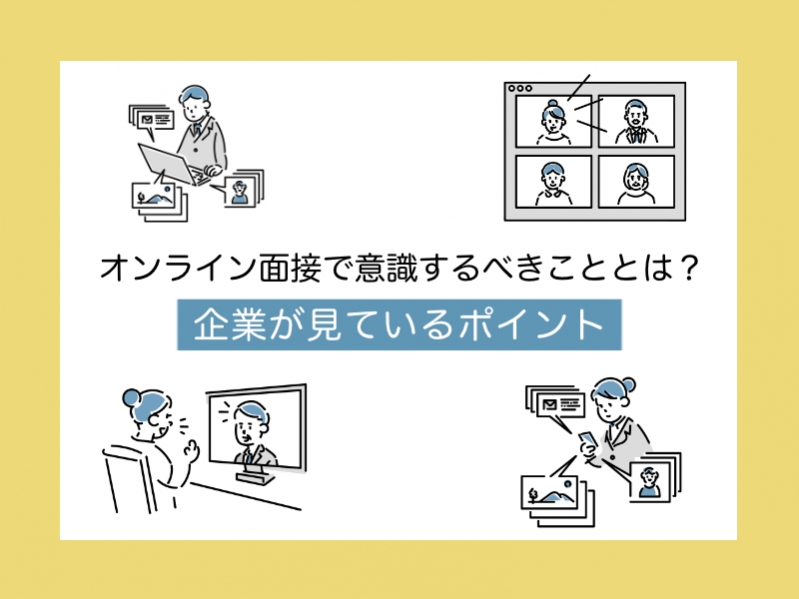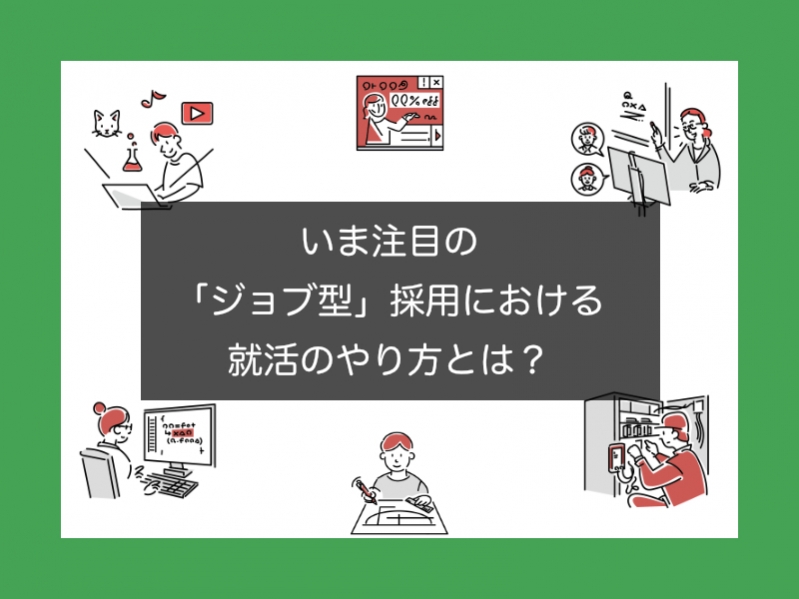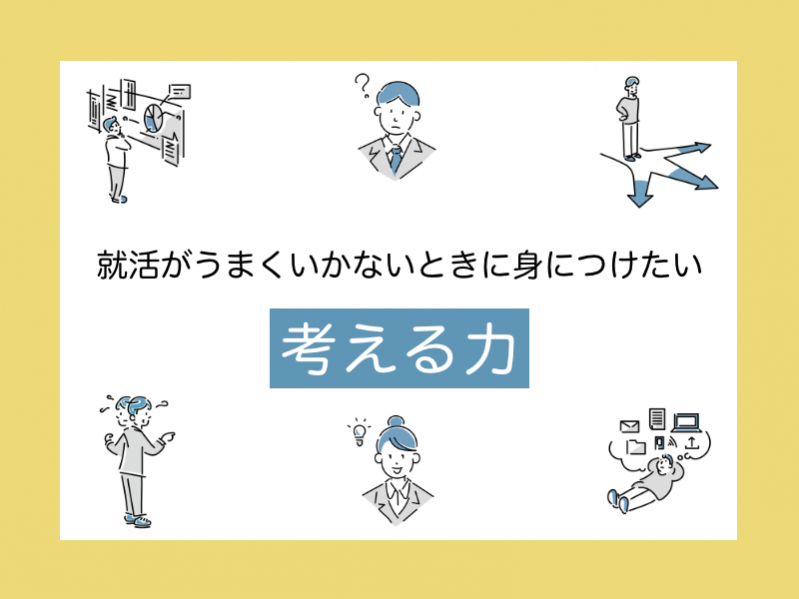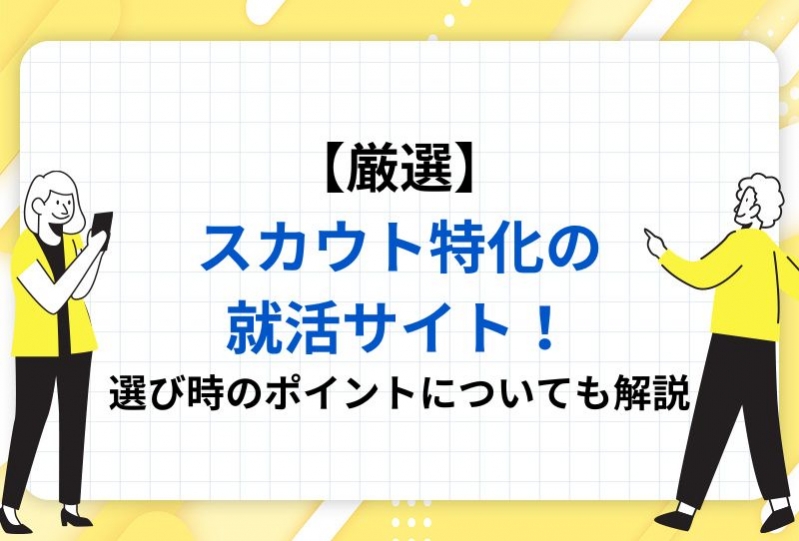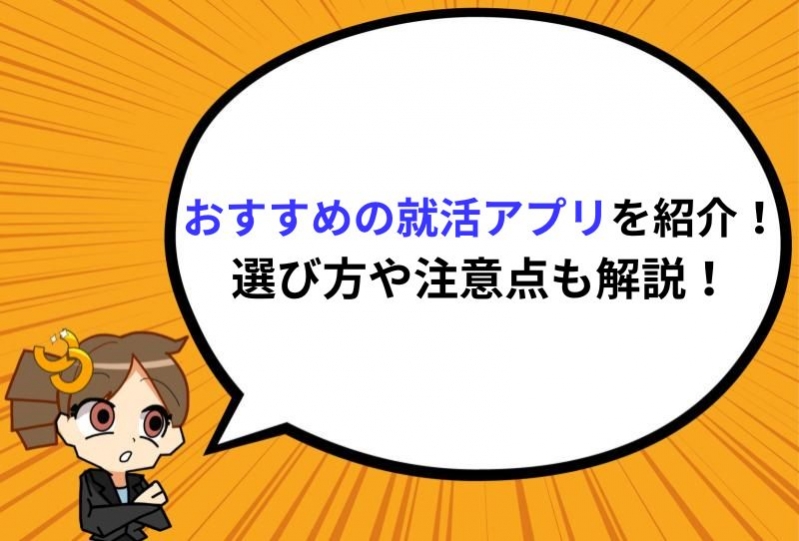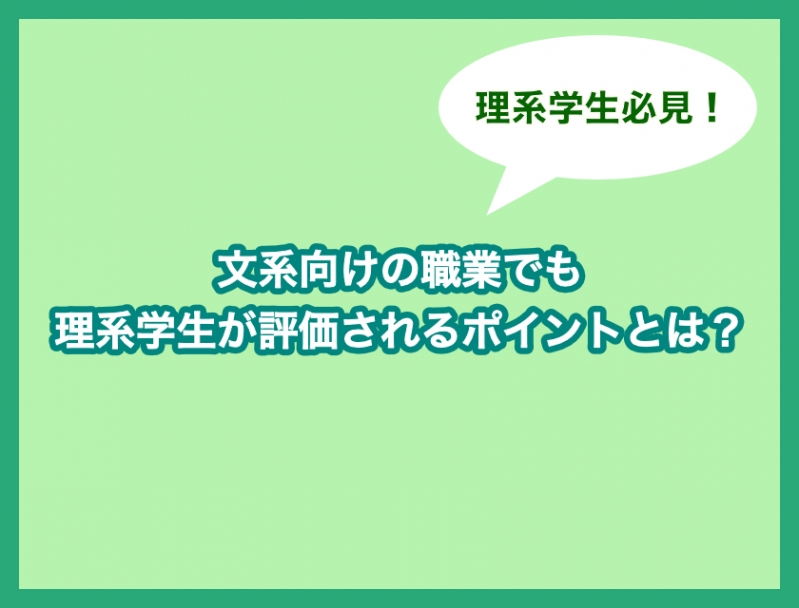【早期のスタートが重要!】「業界研究」の始める時期・進め方を徹底解説
就職活動の第一歩として、「自己分析」を思い浮かべる人は多いかもしれませんが、自己分析と並んで重要なのが「業界研究」です。
特に27卒の皆さんにとっては、いつから業界研究を始めるべきか、どのように進めるべきか、疑問に思うことも多いでしょう。
この記事では、なぜ業界研究が大切なのか、そして具体的に「いつから」「どうやって」業界研究を進めればよいのかを、27卒の皆さんに向けた視点で詳しく解説していきます。
早期に業界研究を始めることが、納得のいく内定を勝ち取るために重要になるため、ぜひ最後まで読んでみてください。
1.なぜ業界研究が必要なのか?
就活の軸を明確にするため
業界研究は、皆さんの「就活の軸」を明確にする上で不可欠です。例えば、「人の役に立ちたい」という漠然とした思いがあっても、それがIT業界でシステム開発を通じて実現できるのか、医療業界で人々の健康を支えることで実現できるのかでは、大きく方向性が異なります。
それぞれの業界が社会に提供する価値や、そこで働く人々の役割を理解することで、自分自身の興味や価値観に本当に合った分野を見つけ出すことができます。これにより、企業選びの基準が明確になり、無駄なく効率的に就職活動を進められるのです。
ミスマッチを防ぎ、入社後の後悔をなくすため
就職活動の失敗談としてよく聞かれるのが、「入社してみたら想像と違った」というミスマッチです。これは、業界や企業への理解が不足しているために起こることがほとんどです。
業界研究を深めることができれば、その業界特有の働き方、企業文化、将来性、そしてやりがいや厳しさといった「リアルな姿」を把握できます。
これにより、自分の性格やライフスタイル、キャリアプランに合った業界や企業を選ぶことができ、入社後のギャップを最小限に抑えることが可能になるでしょう。
志望動機に説得力を持たせるため
選考プロセスにおいて、面接官が最も重視するポイントの一つが「なぜこの業界で、この会社で働きたいのか」という志望動機です。
表面的な情報だけでなく、業界の動向や課題、その中で企業がどのような位置づけで、どのような強みを持っているかを理解していると、深みのある説得力のある志望動機を語ることができます。
これは、単に企業の事業内容を知っているだけでなく、業界全体を俯瞰し、その中で自身の貢献意欲を示すことにつながります。採用担当者は、皆さんの業界への理解度から、入社への本気度や適性を見極めているのです。
2.27卒は「いつから」業界研究を始めるべき?
そもそも就活はいつから始まるのか
27卒における就活は、2025年4月〜6月頃にスタートするのが理想だと考えられています。その理由は、8月頃から開催するサマーインターンシップの説明会や申込を6月前後にスタートする企業が多いからです。
「インターンシップは就職活動に必須ではない」と思う方もいるかもしれませんが、25卒以降の就活で適用されるようになった新ルールにより、インターンシップは採用直結に繋がる重要なものとなりました。
そのため、インターンシップに参加するための選考に向けて、履歴書やエントリーシートの提出が必要となることが多いため、申込時期である6月までに自己分析や業界・企業研究などを進めておかなければならないと言えるのです。
詳しくはこちらの記事をご覧ください
【27卒】就活はいつから始まる?就活のスケジュール・やるべきことを解説!
業界研究を始める時期
夏に開催されるインターンシップや就活の早期化の流れを踏まえると、業界研究に関しても、大学3年生の4~6月に始めるべきであると断言できます。
就活の動きが本格化する大学3年生の夏以降は、インターンシップや説明会、エントリーシート作成などで非常に忙しくなります。その時期に慌てて業界研究を始めるようでは、情報が偏ったり、十分に深掘りできなかったりする可能性が高いといえるでしょう。
そのため、できるだけ早く業界研究を行い、その上でインターンシップなどに参加して、より研究内容を深めるという流れが理想的であるといえます。また、業界研究と並行して、自己分析も欠かさず行いましょう。
早期スタートのメリット
早期に業界研究を始める最大のメリットは、情報収集に多くの時間を割ける点にあります。焦らずに幅広い業界に目を向け、それぞれの特徴やビジネスモデル、将来性を深く理解することができるでしょう。
また、夏や秋に開催される企業のインターンシップへの応募準備もスムーズに進められます。早期に業界を絞り込むことができれば、志望する業界のインターンシップに狙いを定めて参加でき、早期選考のチャンスを掴む可能性も高まります。
さらに、早期に明確な志望業界が見つかれば、残りの学生生活でその業界に役立つスキルや知識を習得する時間も確保でき、効率的な就活へと繋がるでしょう。
3.業界研究の具体的な進め方
①全体像を把握する
最初のステップは、世の中にどんな業界があるのか、その全体像をざっくりと把握することから始めます。特定の業界に絞り込む前に、まずは広く浅く情報を収集し、興味の対象を広げることが大切です。
例えば、製造業やサービス業、IT業界、金融業界などの代表的な業界の種類をリストアップし、それぞれの定義や特徴を簡単に調べてみるとよいでしょう。
この段階では、あまり深く考えすぎず、「こんな業界があるんだな」「これは面白そうだな」といった直感で構いません。視野を広げることで、これまで知らなかった魅力的な業界に出会える機会であると捉えて進めましょう。
②深掘りして理解を深める
全体像を把握し、いくつかの興味を持った業界が見つかったら、次はそれらの業界をさらに深掘りしていきます。
ここでは、業界専門誌やニュース記事、企業のIR情報などを活用し、より専門的で詳細な情報を集めましょう。各業界の市場動向や競合状況、将来的な課題、そしてその業界が抱える独自の文化や慣習についても理解を深めることが重要です。
さらに、OB・OG訪問や企業説明会、インターンシップへの参加を通して、実際にその業界で働く人々の生の声を聞くのもよいでしょう。
座学だけでは分からないリアルな働き方や職場の雰囲気に触れることで、業界への理解度が格段に深まります。
③自分との接点を見つける
業界研究で得た情報をただ集めるだけでなく、それを「自分自身」と結びつけることが重要です。これまでに深掘りした業界の情報と、自己分析で明らかになった自分の興味、強み、価値観、そして将来のキャリアプランとを照らし合わせてみましょう。
「自分の〇〇という強みは、この業界のどんな課題解決に貢献できるだろう?」「自分が目指す働き方は、この業界で実現できるだろうか?」といった問いを持ち、複数の業界を比較検討し、最終的に「自分が最も活躍でき、やりがいを感じられる」と思える業界を見つけることが、最終的なゴールです。
詳しくはこちらの記事をご覧ください
【就活を始めたばかりの学生必見!】効果的な業界研究のやり方とポイントを徹底解説!
4.業界研究で使えるツール・情報源
就活サイト・就活イベント
多くの就活サイトで「業界図鑑」「業界マップ」といった、業界研究に役立つ情報を発信しています。まずはこうしたコンテンツを活用して、世の中にどのような業界があるのか、全体感を把握しておくとスムーズに業界研究に取りかかれます。
また、就活サイトは業界研究に役立つセミナーなどのイベントを開催しているケースもあるので、イベント情報もチェックしておくとよいでしょう。
業界研究セミナー
その業界や企業に興味を持ってもらうため、就活サイトの運営会社や、実際に企業が「業界研究セミナー」を開催しているケースもあります。
企業が開催する業界研究セミナーは、その業界の最新の動向を学べるだけでなく、その業界で働くやりがいや厳しさなどについて、社員から生の声を聞くチャンスでもあるため、よりリアルな情報を得ることができるでしょう。
書籍・雑誌
ネットでの情報だけではなく、書籍や情報雑誌、新聞などの紙媒体の情報も、業界研究を行う上で利用できるツールです。
特に、『会社四季報 業界地図』という書籍では、180以上の業界と各業界の主要企業が掲載されており、業界の最新事情が大まかに理解できる書籍になっています。
このような業界地図で全体像を把握した後、志望業界がある程度絞られてきたら、その業界に特化した情報誌などをチェックしてみるとよいでしょう。
また、日本経済新聞などの大手新聞でビジネス全般の動向を押さえた後、「日本流通産業新聞」「金融経済新聞」といった専門誌・業界紙で気になる業界の実情を深掘りしてみるのもおすすめです。
業界団体のホームページ等
多くの業界には、その業界に所属する企業が集まる業界団体が存在します。「○○業協会」「○○協同組合」「○○連合会」など名称はさまざまで、規模も大小あります。
必ずしも就活に役立つ情報が得られるとは限りませんが、ホームページや広報誌などで、その業界の現状などを発信している業界団体もあります。ほかではなかなか得られないコアな情報が手に入ることもあるので、チェックしてみる価値はあるでしょう。
OB・OG訪問
業界研究をするにあたっては、OB・OG訪問の機会も積極的に活用しましょう。
ある程度志望業界が絞られてきたら、業界研究を一段掘り下げて、仕事のやりがいや厳しさ、その業界で求められる人材などを知るフェーズに入ってきます。
こうした情報は書籍やインターネットよりも、実際にその業界で働いている人から得るのがおすすめです。OB・OG訪問でリアルな一時情報にふれることは、志望動機や自己PRの作成に役立つだけでなく、入社後のミスマッチ防止にもつながります。
キャリアアドバイザーに相談
自分1人で業界研究をしていると、「これで本当に合っているのか?」「どこまで業界研究をすればよいのか?」など、誰かに確認や相談をしてもらいたいと感じると思います。
そこで、就活のプロであるキャリアアドバイザーを頼るのも一つの方法です。業界研究に役立つ情報やおすすめのセミナーなどを紹介してくれる可能性があります。加えて、面接練習や自己分析の方法など、就職活動に役立つアドバイスや選考対策も提供してくれます。
5.業界研究のコツ
「広く浅く」⇒「狭く深く」の順番で進める
業界研究をスタートしたら、まずは広く浅く、世の中にあるさまざまな業界について知るようにしましょう。
特に、BtoBが中心の業界は私たちの日常生活になじみが薄いため、最初は興味が持てない人もいるかもしれません。しかし、知らないから興味がないだけで、少しでも知ってみると魅力的に映る可能性もあります。
だからこそ、最初の「広く浅く」知る段階では、できるだけ「食わず嫌い」をせず、さまざまな業界に視野を広げることを意識することが重要です。世の中にある業界の全体像を捉えることができた上で、興味のあるいくつかの業界を「狭く深く」知る段階に入っていきましょう。
さまざまなツール・手段を併用する
業界研究をするにあたっては、「使えるものは何でも活用する」という姿勢を持つようにしてください。
「インターネットだけに頼る」あるいは「家の中でできることだけをする」というのではなく、インターネット、書籍、新聞とさまざまな媒体を組み合わせるのはもちろん、セミナーやOB・OG訪問といったリアルな場にも出かけて、多角的な情報を得るようにするといいでしょう。
結局、家の中でできるリサーチで終わってしまうと、「その他大勢」が持っている情報しか得られません。セミナーに参加する、OB・OG訪問をするなど、積極的に外に出た人だけが得られる「生きた情報」があることを肝に銘じておきましょう。
6.まとめ
業界研究は、単に情報を集めることではありません。自身の興味や強みと照らし合わせながら、本当に活躍できる業界を見つけるために重要であり、入社後のミスマッチを防ぐための重要なステップです。
そして、志望動機や自己PRなどに説得力を持たせるためにも、業界への深い理解は不可欠となります。
まずは、就活サイトやセミナー、業界誌などを最大限に活用し、広く浅く研究を進めましょう。そして、興味のある業界が見えてきたら、より視野を絞って深く研究をしていき、インターンで得られるものが多くなるように準備しておくことが重要です。
27卒の皆さんは、就活の早期化や採用直結インターンシップといった現状を踏まえ、サマーインターンの選考が始まる前(6~7月頃)には業界研究を始めておくとよいでしょう。